
煉瓦研究ネットワーク東京 フィールドワーク11 上野・荒川編4 上野から荒川への移動
フィールドワーク東京藝術大学1号館、2号館を見学させていただいた後は、過去の取り壊した建物の煉瓦の集積所に案内されて調査した。 一部は芸大だけではなく東大で取り壊された建物の煉瓦も集積されている。一つ一つ手に取り、刻印の有無と、刻印の形[…]
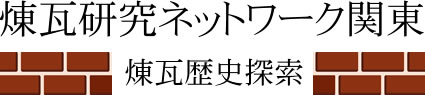

東京藝術大学1号館、2号館を見学させていただいた後は、過去の取り壊した建物の煉瓦の集積所に案内されて調査した。 一部は芸大だけではなく東大で取り壊された建物の煉瓦も集積されている。一つ一つ手に取り、刻印の有無と、刻印の形[…]

前回ご紹介させて頂いた1号館が次の写真である。 この1号館の後ろに立つ3階建ての煉瓦の建物が2号館である。 2号館は1号館に遅れること6年、1886年(明治19年)に東京図書館書籍閲覧所として建てられた。 設計は、アメリ[…]

東京藝術大学のキャンパスの真ん中を東西に都道452号が走っている。 1918年(大正7年)にこの都道が作られると、都道に対して南北対象に煉瓦造りの校門が作られた。残念ながら、現在は、都道北側に面したものしか残っていない。[…]

5月27日日曜日、第4回目となる『煉瓦研究ネットワーク東京』のフィールドワークは、13時に上野駅公園口をスタートして、最初の目的地である東京芸術大学へと向かった。 今回は上野をスタートして、荒川区の煉瓦遺構を巡るコースで[…]

前回ご紹介した八王子市内の小学校に残るフランス積みの煉瓦塀を見学すると、甲州街道を高尾へと向かった。 当初の予定では、さらにここから数箇所回る予定であったが、今まで巡ってきたところで時間をかけすぎたため予定を変更して、甲[…]

先週の金曜日、葛飾から帰る途中新橋駅のホームを見ると、京浜東北線北行き、山手線内回りホームの煉瓦部分の一部を削り取っていたのが見えたので、写真に収めました。 新橋駅開業当時の煉瓦積みですが、この写真から考えられることは、[…]

京王八王子駅近くの福伝寺を後にすると、甲州街道を下り追分町近くの八王子市内のある小学校へと向かった。 この小学校の歴史は古く、ホームページを確認すると1873年(明治6年)までさかのぼる。 現在地に移転してきた1891年[…]
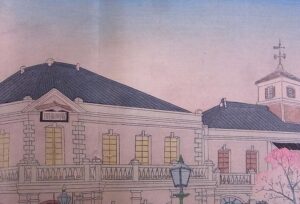
1872年(明治5年)4月5日午後3時頃、和田倉門内の兵部省から出火した火災は、丸の内から銀座、築地と燃え広がり、95万㎡を焼き尽くして午後10時過ぎに鎮火した。世に言われる「銀座大火」だ。 政府はお雇い外国人でアイルラ[…]

前回は、1901年(明治34年)中央線開通当時の第二石曽根橋梁をご紹介した。今回は、そこから程近い京王八王子駅近くの福伝寺にあるものをご紹介しよう。 境内脇の墓所に行くと、中心部にひときわ目立つ煙突のような墓標が異彩を放[…]

前回は甲武鉄道の旧八王子駅に続く遺構の跡をご紹介したが、今日は中央線開通当時の橋梁をご紹介しよう。 1901年(明治34年)に八王子⇔塩尻間が開通したときに、旧八王子駅から現在の八王子駅に線路が付け替えられたといわれてい[…]